神納川本流


風屋ダム湖をまたぐ旧吊り橋(現在は新橋が出来て通行禁止)

護摩壇山を水源とする深い谷筋


十津川村の象徴となっている「谷瀬のつり橋」からさらに車で十数分南下すると、十津川は深く水をたたえるようになる。風屋ダム湖だ。風屋トンネルを抜けてすぐ右折。ダム湖をまたいで西に走る。バックウオーターの水が切れる頃、広大な河原が現れる。神納川本流だ。大きな蛇行を繰り返しながら川は伯母子岳と護摩壇山を結ぶ稜線の南東斜面まで駆け上る。支流も多い長大な支流である。
かつて神納川といえば十津川の渓流釣り場の本拠地のようにさえ言われた。天然大型アマゴの伝説をほしいままにした有名渓谷である。しかし、僕が本格的に渓流釣りを始めた35年前にはすでに、神納川は大量の砂利に埋まってしまっていた。源流部の大規模森林伐採のために。深く切れ込んだV字形の谷筋は林道からの見通しがよく、近年、米軍ジェット戦闘機の訓練が横行し、架線ワイヤー切断が後を絶たないことで社会問題になった場所でもある。実際僕も何度も激しい爆音に驚かされたことがあるし、手の届きそうな低空を猛烈なスピードで空を切り裂いて飛ぶ飛行機を一回目撃した。飛行機は広いV字の谷に沿って飛ぶ。右岸と左岸を結ぶ木材搬出架線を切るのは当然だった。むしろ大惨事にならなかったのが不思議なくらいだ。
神納川は中流部の五百瀬(イモゼ)までは平坦な瀬が続く大河。中流部からは大岩がごろごろと重なり、それは源流部まで続く。上に登っていくほどに山の木は激しく伐採され、荒涼としてまるで異国の風景を見るようだ。林道と川面の距離はますます離れ、空が近くなる。谷に入るには数十分もかけて、きつい坂道を下らなければならない。蛇行を繰り返す谷では、方向感覚を失うことが多い。斜面を息も絶え絶えに登ったところが、林道とはまったく違った尾根に上がっていたということも何度かあった。伐採の山は土が緩く、帰り道、林道が半分失せてしまって、車幅ぎりぎりを運を天にまかせて走り抜けたこともある。落ちればまさに奈落の底。200メートルの断崖から車もろとも落ちていく夢をその後何度か見た。
神納川に注ぐ谷は、谷も深くそこそこ水量もあって魅力的だ。本流をはじめ、各支流の多さから神納川に通う釣り人は多い。
大黒谷は、旧吊り橋を渡ってすぐ南側に開く谷(現在は新橋を渡ると少し戻ることになる)で、開口部は広く、堰堤が重なって続く。堰堤と堰堤の間は平坦でチャラ瀬だが、奥に入るにつれて厳しい渓相になり、ゴロ岩に囲まれた廊下が現れる。小滝と壺が連続する。竿を畳んでは上り、釣っては畳むことの繰り返しになる。最近は渓流登山の愛好者もよく入ると聞く。どこまで入るかは帰りの体力と相談になる。
榎谷
榎谷は神納川下流部左岸にある谷で、右岸沿いに走る林道からはその入り口は遠く山陰に隠れ、谷の存在すらわからない。わりとマニアックな谷である。行き方は2通りある。ひとつは、本流に降りて、伏流(谷はあるが水は底を流れていて見かけ上、枯れた谷)になっている谷の入り口から谷通しで登っていく方法。もうひとつは、林道が対岸にわたったところから山天という集落に向かう山道を行き、終点で車を捨てて1時間歩く方法。こちらは、榎谷の中流部に出る。下流からのアタックは、ごろ石の段差のある渓流。中流からは平坦な瀬のある渓流となる。魚は小型だが魚影はけっこう濃い。あっ、こういうことを書いてはいけないのだった。
三田谷
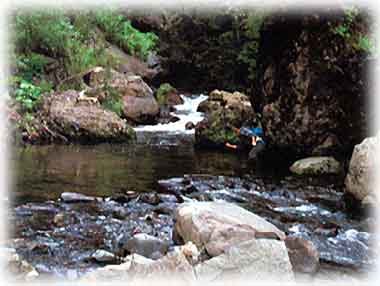 三田谷と書いてビタダニと言う。ちなみに神納川はカンノガワだ。僕はどういうわけか神納川支流の谷のなかで一番のお気に入りの谷でよく通った。この谷も本流合流付近は伏流である。(2006年現在、河川工事で溝になっている。なんのための工事かまったく理解できない。)榎谷に比べるとその川幅は大きく、谷が開けて明るい感じ。しかし、川原の広さの割に細い水流で、ちろちろと水が流れている。美しい水なのですぐ竿を出したくなるが、ここは辛抱する。ここらで竿を出す人は、絶対に良い釣果に恵まれない。半日も釣りをして、そろそろ帰ろうかなと思う頃から、がぜん谷は渓流の雰囲気を示してくれるからだ。だから、ひたすら歩く。水の流れを見ながらひたすら谷をさかのぼって歩く。約1時間、ここでやっと竿を出す。ここまで竿を出さずに辛抱すると、思いもかけない釣果に恵まれる(かもしれない)。入り口ののんびりとした渓相からは想像できない、うっそうとした美しい渓流に出逢えるだろう。 三田谷と書いてビタダニと言う。ちなみに神納川はカンノガワだ。僕はどういうわけか神納川支流の谷のなかで一番のお気に入りの谷でよく通った。この谷も本流合流付近は伏流である。(2006年現在、河川工事で溝になっている。なんのための工事かまったく理解できない。)榎谷に比べるとその川幅は大きく、谷が開けて明るい感じ。しかし、川原の広さの割に細い水流で、ちろちろと水が流れている。美しい水なのですぐ竿を出したくなるが、ここは辛抱する。ここらで竿を出す人は、絶対に良い釣果に恵まれない。半日も釣りをして、そろそろ帰ろうかなと思う頃から、がぜん谷は渓流の雰囲気を示してくれるからだ。だから、ひたすら歩く。水の流れを見ながらひたすら谷をさかのぼって歩く。約1時間、ここでやっと竿を出す。ここまで竿を出さずに辛抱すると、思いもかけない釣果に恵まれる(かもしれない)。入り口ののんびりとした渓相からは想像できない、うっそうとした美しい渓流に出逢えるだろう。
山を高巻きして中流部に行ったこともあるが、これは逆に重労働になるので、川を歩くに限る。だからこの谷の定員は1名のみ。ある日、深夜に入り口に着き仮眠して早朝から出発。汗かきかき1時間歩いて竿を出し、さあ、これからというときに前方の岩陰に釣り人の姿を見たときには、愕然とした。仮眠中に、後から来た人に、先に入られてしまっていたという次第である。こんな時には、早々に引き上げるに限る。ただし、その日は釣ったかもしれない大物の幻想に一日悩まされることだけは避けられないが。
 小本流中流部の右岸に流れ込む谷。林道からは見えない。徒歩で右岸に渡るつり橋を越えて谷に入る。入り口から竿を出したい欲求にかられる素敵な渓相だが、これが南股谷の詐欺である。魚影はきわめて薄い。この谷も左岸沿いの山道を登り、尾根づたいの道をひたすた1時間以上歩く必要がある。写真は山道の途中で出くわしたシャクナゲの群生林。たまたま5月の下旬頃だったと思うが、満開のシャクナゲに遭遇した。そこら一帯が淡いピンクの花で埋め尽くされていた。シャクナゲといえば、高山の代表花だが、乱獲されめっきり自然の姿を見ることは少なくなってしまった。植木市などに並んでいる鉢植えの姿を想像してはいけない。ひとかかえもあるような巨木の群生に花が鈴なりについているのだ。シャクナゲの花期は短い。偶然とはいえほんとうにラッキーだった。花がなければ、ただの森としか見えなかっただろううっそうとした尾根の道。シャクナゲのトンネルはどんな遊園地のどんな見せ物よりも素敵だった。もう何年もここに行ってないが、あの群生シャクナゲは今も同じように咲いているのだろうか。 小本流中流部の右岸に流れ込む谷。林道からは見えない。徒歩で右岸に渡るつり橋を越えて谷に入る。入り口から竿を出したい欲求にかられる素敵な渓相だが、これが南股谷の詐欺である。魚影はきわめて薄い。この谷も左岸沿いの山道を登り、尾根づたいの道をひたすた1時間以上歩く必要がある。写真は山道の途中で出くわしたシャクナゲの群生林。たまたま5月の下旬頃だったと思うが、満開のシャクナゲに遭遇した。そこら一帯が淡いピンクの花で埋め尽くされていた。シャクナゲといえば、高山の代表花だが、乱獲されめっきり自然の姿を見ることは少なくなってしまった。植木市などに並んでいる鉢植えの姿を想像してはいけない。ひとかかえもあるような巨木の群生に花が鈴なりについているのだ。シャクナゲの花期は短い。偶然とはいえほんとうにラッキーだった。花がなければ、ただの森としか見えなかっただろううっそうとした尾根の道。シャクナゲのトンネルはどんな遊園地のどんな見せ物よりも素敵だった。もう何年もここに行ってないが、あの群生シャクナゲは今も同じように咲いているのだろうか。
小井谷

南股谷を過ぎ源流部に近づくと、林道はぐんぐん標高をかせぐように山の稜線に向かって登っていく。はるか左下に見える神納川本流がいつの間にか、急に細い渓流になっている。 実は、林道は本流から離れ、支流の小井谷に沿って登っているのだが、合流点が見えないので、急に本流が細くなってしまったような錯覚に陥るのだ。本流がはげしく蛇行し(180度方向を転換するところもある)ているために、本流なのか支流なのか、また、谷はどちらに向かって流れているのかわからなくなることがある。
本流の釣りは、蛇行を常にイメージして歩かないとまったく方向を見失い、谷から上がるときに、とんでもない山の峰に出てしまうことがある。上方の写真は小井谷からさらに上流部の東又谷の左岸稜線に立っている本人である(ずいぶん若い)。午前中の釣りが終わってちょっと休憩中。タイマーでパシャッと一枚。僕はほとんど単独行なのでこうして自分が写っている写真は少ない。かっこつけちゃってさ。丸裸の荒涼とした山は異様だ。お世辞にも美しいといえない。向こうに見えるのは伯母子岳の南側稜線だ。尾根筋にわずかばかりの原生林を残しているのは境界を示すためなのだろうか。撮影ポイント、標高1300メートル付近。空がほんとうに近い。海のように青い空が印象的だ。
|






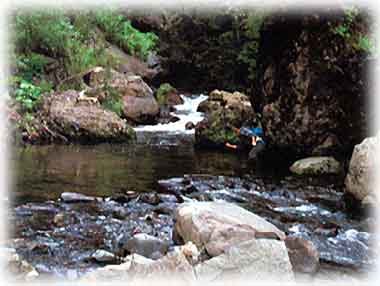 三田谷と書いてビタダニと言う。ちなみに神納川はカンノガワだ。僕はどういうわけか神納川支流の谷のなかで一番のお気に入りの谷でよく通った。この谷も本流合流付近は伏流である。(2006年現在、河川工事で溝になっている。なんのための工事かまったく理解できない。)榎谷に比べるとその川幅は大きく、谷が開けて明るい感じ。しかし、川原の広さの割に細い水流で、ちろちろと水が流れている。美しい水なのですぐ竿を出したくなるが、ここは辛抱する。ここらで竿を出す人は、絶対に良い釣果に恵まれない。半日も釣りをして、そろそろ帰ろうかなと思う頃から、がぜん谷は渓流の雰囲気を示してくれるからだ。だから、ひたすら歩く。水の流れを見ながらひたすら谷をさかのぼって歩く。約1時間、ここでやっと竿を出す。ここまで竿を出さずに辛抱すると、思いもかけない釣果に恵まれる(かもしれない)。入り口ののんびりとした渓相からは想像できない、うっそうとした美しい渓流に出逢えるだろう。
三田谷と書いてビタダニと言う。ちなみに神納川はカンノガワだ。僕はどういうわけか神納川支流の谷のなかで一番のお気に入りの谷でよく通った。この谷も本流合流付近は伏流である。(2006年現在、河川工事で溝になっている。なんのための工事かまったく理解できない。)榎谷に比べるとその川幅は大きく、谷が開けて明るい感じ。しかし、川原の広さの割に細い水流で、ちろちろと水が流れている。美しい水なのですぐ竿を出したくなるが、ここは辛抱する。ここらで竿を出す人は、絶対に良い釣果に恵まれない。半日も釣りをして、そろそろ帰ろうかなと思う頃から、がぜん谷は渓流の雰囲気を示してくれるからだ。だから、ひたすら歩く。水の流れを見ながらひたすら谷をさかのぼって歩く。約1時間、ここでやっと竿を出す。ここまで竿を出さずに辛抱すると、思いもかけない釣果に恵まれる(かもしれない)。入り口ののんびりとした渓相からは想像できない、うっそうとした美しい渓流に出逢えるだろう。 小本流中流部の右岸に流れ込む谷。林道からは見えない。徒歩で右岸に渡るつり橋を越えて谷に入る。入り口から竿を出したい欲求にかられる素敵な渓相だが、これが南股谷の詐欺である。魚影はきわめて薄い。この谷も左岸沿いの山道を登り、尾根づたいの道をひたすた1時間以上歩く必要がある。写真は山道の途中で出くわしたシャクナゲの群生林。たまたま5月の下旬頃だったと思うが、満開のシャクナゲに遭遇した。そこら一帯が淡いピンクの花で埋め尽くされていた。シャクナゲといえば、高山の代表花だが、乱獲されめっきり自然の姿を見ることは少なくなってしまった。植木市などに並んでいる鉢植えの姿を想像してはいけない。ひとかかえもあるような巨木の群生に花が鈴なりについているのだ。シャクナゲの花期は短い。偶然とはいえほんとうにラッキーだった。花がなければ、ただの森としか見えなかっただろううっそうとした尾根の道。シャクナゲのトンネルはどんな遊園地のどんな見せ物よりも素敵だった。もう何年もここに行ってないが、あの群生シャクナゲは今も同じように咲いているのだろうか。
小本流中流部の右岸に流れ込む谷。林道からは見えない。徒歩で右岸に渡るつり橋を越えて谷に入る。入り口から竿を出したい欲求にかられる素敵な渓相だが、これが南股谷の詐欺である。魚影はきわめて薄い。この谷も左岸沿いの山道を登り、尾根づたいの道をひたすた1時間以上歩く必要がある。写真は山道の途中で出くわしたシャクナゲの群生林。たまたま5月の下旬頃だったと思うが、満開のシャクナゲに遭遇した。そこら一帯が淡いピンクの花で埋め尽くされていた。シャクナゲといえば、高山の代表花だが、乱獲されめっきり自然の姿を見ることは少なくなってしまった。植木市などに並んでいる鉢植えの姿を想像してはいけない。ひとかかえもあるような巨木の群生に花が鈴なりについているのだ。シャクナゲの花期は短い。偶然とはいえほんとうにラッキーだった。花がなければ、ただの森としか見えなかっただろううっそうとした尾根の道。シャクナゲのトンネルはどんな遊園地のどんな見せ物よりも素敵だった。もう何年もここに行ってないが、あの群生シャクナゲは今も同じように咲いているのだろうか。